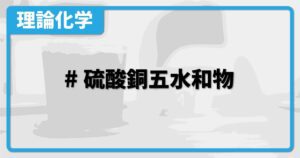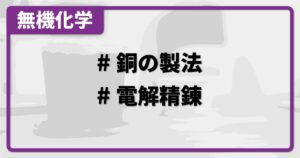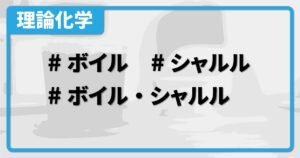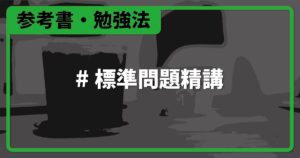MENU
イオン分析を行う上で必要な知識まとめ
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『イオン分析を行う上で必要な知識まとめ』について解説しています。
沈殿生成反応
- 沈殿生成反応を利用することで水溶液中に含まれるイオンを判断することができる。
- 例えば硫酸イオンSO42ーはCa2+、Sr2+、Ba2+、Pb2+と沈殿をつくりやすいので、硫酸を加えて沈殿を生成したら水溶液中にはこれらのイオンのうちどれかが存在することが予測できる。
イオン・化合物(沈殿)の色
- 2本の試験管があり片方にはZn2+、もう片方にはPb2+を含んだ水溶液が入っているとする。
- ここで両方の試験管に硫化水素H2Sを通じたところ、一方には黒色の沈殿が、もう一方には白色の沈殿が生じたとする。
- 水に難溶なイオン結晶(水酸化物・硫化物・塩化物・硫酸・クロム酸・炭酸イオン)にあるように、中性下でH2Sを通じた場合、Zn2+とPb2+はともに硫化物の沈殿を生成する。
- したがって、単に沈殿が生成するということを知っていただけでは、どちらの試験管にZn2+またはPb2+が含まれるのか判断できない。
- しかし、ZnSの色が白色であり、PbSの色が黒色であることを知っていれば、試験管にZn2+とPb2+のどちらが含まれているかを見分けることができる。
- この判別法を行うにはイオンや沈殿に関して知識をもっておく必要がある。詳しくは次のページを参照のこと。
炎色反応
- ある元素が含まれた水溶液を炎の中に入れると、その元素特有の色を示す。これを炎色反応という。
- 炎色反応は水溶液に含まれているアルカリ金属元素やアルカリ土類金属元素を調べる目的などで利用される。
- 炎色反応について詳しくは次のページを参照のこと。
沈殿を溶かす方法
- 沈殿を溶かす方法は、複数の沈殿が混ざって生成したときにそれらを再溶解させて再度イオン分析を進めるときに役立つ。
- ここでは代表的な3つの方法を紹介する。
中和反応
- 中和反応を利用して沈殿を溶かすことができる。
- 例えば水酸化鉄(Ⅲ)の沈殿に塩酸を滴下すると中和反応により沈殿が溶解する。
\[ \mathrm{Fe(OH)_{3}↓ + 3H^{+} → Fe^{3+}+3H_{2}O} \]
弱酸遊離反応
- 弱酸遊離反応を利用して沈殿を溶かすことができる。
- 例えば炭酸カルシウムCaCO3の沈殿に塩酸を滴下すると、弱酸遊離反応によって沈殿が溶解する。
\[ \mathrm{CaCO_{3}↓ + 2H^{+} → Ca^{2+}+H_{2}O+CO_{2}} \]
参考:【弱酸・弱塩基遊離反応】原理や公式、反応式の作り方など
錯イオン形成反応
- 錯イオン形成反応を利用して沈殿を溶かすことができる。
- 例えば水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2の沈殿に過剰のアンモニア水を加えると錯イオン形成反応により沈殿が溶解する。
\[ \mathrm{Cu(OH)_{2}↓+4NH_{3}→[Cu(NH_{3})_{4}]^{2+}+2OH^{-}} \]
鉄のイオンの検出反応
- 鉄の陽イオンには2価の鉄(Ⅱ)イオンFe2+と3価の鉄(Ⅲ)イオンFe3+が存在する。
- 水溶液中にどちらが存在するかを見分けるときにはヘキサシアニド鉄酸カリウム又はチオシアン酸カリウムを用いる。
ヘキサシアニド鉄酸カリウムを用いる方法
| イオン | 操作 | 沈殿の色 |
|---|---|---|
| Fe2+ | 鉄(Ⅱ)イオンFe2+にヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウムK3[Fe(CN)6]を加える | 濃青色↓ |
| Fe3+ | 鉄(Ⅲ)イオンFe3+にヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムK4[Fe(CN)6]を加える | 濃青色↓ |
- Fe2+を含む水溶液にヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウムK3[Fe(CN)6]を加える又はFe3+を含む水溶液にヘキサシアニド鉄(Ⅱ)酸カリウムK4[Fe(CN)6]を加えると濃青色の沈殿を生じる。
チオシアン酸カリウムを用いる方法
| イオン | 操作 | 溶液の色 |
|---|---|---|
| Fe3+ | チオシアン酸カリウムKSCNを加える | 血赤色aq |
- Fe3+を含む水溶液にKSCNを加えると溶液が血赤色になる。(沈殿ではないことに注意)
- Fe2+ではこの反応は起こらないので判別できる。
ハロゲン化銀の反応
- ハロゲン化銀の反応を確認する。
水への溶解性
- ハロゲン化銀のうちフッ化銀AgFのみが水に溶けやすく、塩化銀AgCl、臭化銀AgBr、ヨウ化銀AgIは水に溶けにくい。
アンモニア水を加えた場合
- 今説明したようにAgCl、AgBr、AgIは溶けにくい沈殿だが、AgCl、AgBrの沈殿は、過剰のアンモニア水を加えると錯イオンを形成して溶ける。
\[ \mathrm{AgCl+2NH_{3}→[Ag(NH_{3})_{2}]^{+}+Cl^{-}} \]
- 一方、AgIは溶解度が非常に小さいのでこの反応でも溶けない。
チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えた場合
- AgCl、AgBr、AgIの沈殿は、チオ硫酸ナトリウムNa2S2O3水溶液を加えると錯イオンを形成して溶ける。
\[ \mathrm{AgCl→2S_{2}O_{3}^{2-}→[Ag(S_{2}O_{3})_{2}]^{3-}+Cl^{-}} \]
シアン化カリウム水溶液を加えた場合
- AgCl、AgBr、AgIの沈殿は、シアン化カリウムKCN水溶液を加えると錯イオンを形成して溶ける。
\[ \mathrm{AgCl→2CN^{-}→[Ag(CN)_{2}]^{-}+Cl^{-}} \]