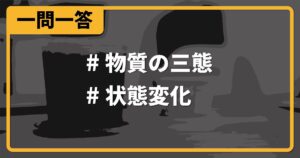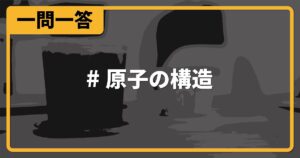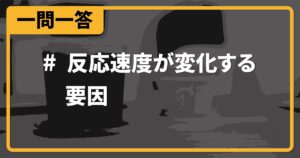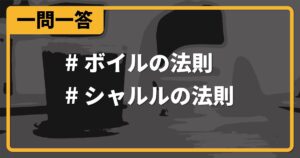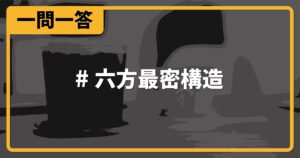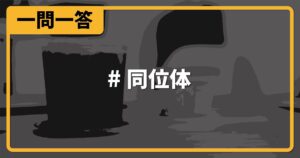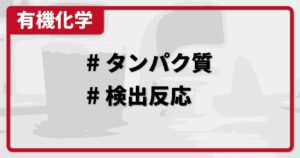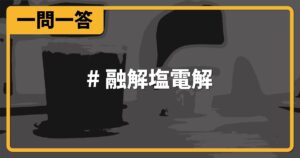MENU
タンパク質【高校化学・化学基礎一問一答】
タンパク質を構成するポリペプチド鎖のアミノ酸の結合順序をタンパク質の【1】構造という。
解答/解説:タップで表示
ペプチド鎖中のペプチド結合同士が水素結合により、局部的に一定な構造を取ることがある。これをタンパク質の【1】構造という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】二次
ペプチド鎖中のペプチド結合同士が水素結合により、局部的に一定な構造を取ることがある。これをタンパク質の二次構造という。
タンパク質の二次構造には、【1】構造と【2】構造が存在する。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】α-ヘリックス【2】β-シート(順不同)
タンパク質の二次構造には、α-ヘリックス構造とβ-シート構造が存在する。
タンパク質のペプチド鎖は多くの場合、【1(右 or 左)】巻きらせん構造をとる。このらせん構造を【2】構造という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】右【2】α-ヘリックス
タンパク質のペプチド鎖は多くの場合、右巻きらせん構造をとる。このらせん構造をα-ヘリックス構造という。
三次元的な空間配置まで含めた分子鎖全体の構造をタンパク質の【1】構造という。
解答/解説:タップで表示
三次構造を安定化させている結合のうち最も強い結合は【1】である。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】ジスルフィド結合(S-S結合)
三次構造を安定化させている結合のうち最も強い結合はジスルフィド結合(S-S結合)である。
ジスルフィド結合はタンパク質を構成しているアミノ酸に【1】が含まれるときに形成される。
解答/解説:タップで表示
ジスルフィド結合は三次構造を支える結合の中で唯一の【1】結合であり、最も【2(強 or 弱)】い結合である。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】共有【3】強
ジスルフィド結合は三次構造を支える結合の中で唯一の共有結合であり、最も強い結合である。
参考:タンパク質の一次構造・二次構造(αヘリックス/βシート)・三次構造・四次構造
参考:共有結合(例・イオン結合や配位結合との違いなど)
側鎖にある【1(極 or 無極)】性で【2(親水 or 疎水)】性の炭化水素基やベンゼン環などは、水との接触ができる限り【3(多 or 少な)】くなるように連結する。これを【4】結合といい、この結合は疎水基の数が【5(多 or 少な)】くなるほど強力な結合となる。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】無極【2】疎水【3】少な【4】疎水【5】多
側鎖にある無極性で疎水性の炭化水素基やベンゼン環などは、水との接触ができる限り少なくなるように連結する。これを疎水結合といい、この結合は疎水基の数が多くなるほど強力な結合となる。
三次構造を形成したポリペプチド鎖が複数個会合して、1つの分子になる場合がある。このような分子内でのポリペプチド鎖の配列をタンパク質の【1】構造という。またこのときの各ポリペプチド鎖は【2】とよばれる。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】四次【2】サブユニット
三次構造を形成したポリペプチド鎖が複数個会合して、1つの分子になる場合がある。このような分子内でのポリペプチド鎖の配列をタンパク質の四次構造という。またこのときの各ポリペプチド鎖はサブユニットとよばれる。
アミノ酸のみからなるタンパク質を【1】、アミノ酸の他に糖類やリン酸、核酸、色素などを含むタンパク質を【2】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】単純タンパク質【2】複合タンパク質
アミノ酸のみからなるタンパク質を単純タンパク質、アミノ酸の他に糖類やリン酸、核酸、色素などを含むタンパク質を複合タンパク質という。
ポリペプチド鎖が折りたたまれ、球状になったタンパク質を【1】という。【1】は親水基を【2(外 or 内)】側に、疎水基を【3(外 or 内)】側に向けているため、【4(親水 or 疎水)】コロイドであり、水に溶け【5(やす or にく)】い。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】球状タンパク質【2】外【3】内【4】親水【5】やす
ポリペプチド鎖が折りたたまれ、球状になったタンパク質を球状タンパク質という。球状タンパク質は親水基を外側に、疎水基を内側に向けているため、親水コロイドであり、水に溶けやすい。
複数のポリペプチド鎖が絡み合い、束になっているタンパク質を【1】という。【1】は水に溶け【2(やす or にく)】く、皮膚や髪などの形成に役立っている。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】繊維状タンパク質【2】にく
複数のポリペプチド鎖が絡み合い、束になっているタンパク質を繊維状タンパク質という。繊維状タンパク質は水に溶けにくく、皮膚や髪などの形成に役立っている。
皮膚に含まれる繊維状タンパク質は【1】、髪に含まれる繊維状タンパク質は【2】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】コラーゲン【2】ケラチン
皮膚に含まれる繊維状タンパク質はコラーゲン、髪に含まれる繊維状タンパク質はケラチンという。
加熱等によりタンパク質の立体構造が不可逆的に変化して機能が失われることをタンパク質の【1】という。
解答/解説:タップで表示
α-アミノ酸やタンパク質にニンヒドリン試薬を加えて加熱すると赤紫〜青紫色になる。この反応を【1】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】ニンヒドリン反応
α-アミノ酸やタンパク質にニンヒドリン試薬を加えて加熱すると赤紫〜青紫色になる。この反応をニンヒドリン反応という。
ペプチド結合を2つ以上もつペプチドに水酸化ナトリウム水溶液、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を順に加えると【1】色になる。この反応を【2】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】赤紫【2】ビウレット反応
ペプチド結合を2つ以上もつペプチドに水酸化ナトリウム水溶液、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を順に加えると赤紫色になる。この反応をビウレット反応という。
芳香環をもつアミノ酸(タンパク質)に濃硝酸を加えると【1】色になり、そこにアンモニア水を加えると【2】色になる。この反応を【3】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】黄【2】橙【3】キサントプロテイン反応
芳香環をもつアミノ酸(タンパク質)に濃硝酸を加えると黄色になり、そこにアンモニア水を加えると橙色になる。この反応をキサントプロテイン反応という。
システインのような側鎖に【1】原子を含むアミノ酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱し、それを酢酸で中和して酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると、【2】の【3】色沈殿が生じる。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】硫黄S【2】硫化鉛(Ⅱ)PbS【3】黒
システインのような側鎖に硫黄S原子を含むアミノ酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱し、それを酢酸で中和して酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると、硫化鉛(Ⅱ)PbSの黒色沈殿が生じる。