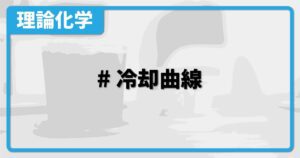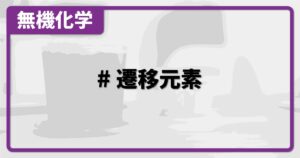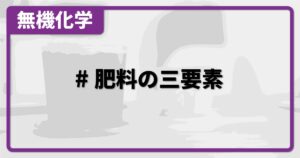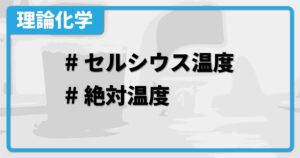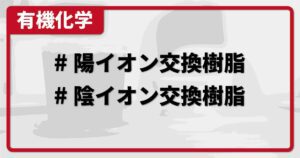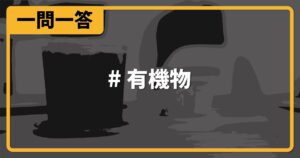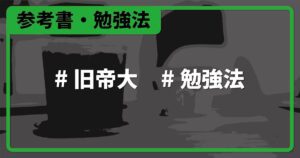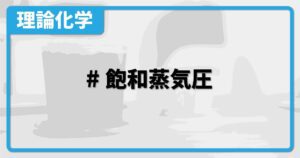MENU
無機物(分類・有機物との違いなど)
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『無機物(分類・有機物との違いなど)』について解説しています。
有機物とは
- 無機物を理解するために,まずは有機物の定義を確認する。
- 数百年前は,生命に関連するものが有機物,それ以外のものが無機物と定義されていた。
- しかし,1828年にドイツ人のウェーラーがシアン酸アンモニウムNH4OCNを加熱することで尿素CO(NH2)2を合成(NH4OCN → CO(NH2)2)してから,有機物(有機化合物)は炭素C原子を含む化合物の総称とされている。
有機物の例外
- 有機物は炭素C原子を含む化合物の総称というのが原則である。ただし,例外として,次の化合物はC原子を含んでいるが無機物に分類される。
- CO・CO2などの酸化物
- CaCO3などの金属元素を含む炭酸塩
- KCNなどのシアン化物
無機物とは
- 無機物とは有機物以外の物質である。つまり,炭素C原子が含まれない物質は全て無機物ということになる。
- 無機物を”単体”と”化合物”に分けて確認する。
単体
- 1種類の元素からなる物質を単体という。
- 定期テストや大学入試で頻出の単体としては,同素体が存在する硫黄S・炭素C・酸素O・リンPなどがある。
- Cは有機物じゃないの?と思う人がいるかもしれないが,先述のように『有機物=炭素C原子を含む”化合物”の総称』である。つまり,有機物は基本的に”化合物”のため,逆に考えると単体として存在しているものは基本的に無機物ということになる。Cも例外ではなく,単体として存在しているときは無機物として扱われる。
化合物
- 無機物の化合物の代表例として,次の4種類が挙げられる。
- 酸化物
- 水酸化物
- オキソ酸
- 塩
- それぞれについて,順番に解説する。
❶ 酸化物
- 酸化された化合物を酸化物という。
- 酸化物には酸性酸化物・塩基性酸化物・両性酸化物があり,例としてはCO2・CaO・Al2O3などがあげられる。
参考:酸性酸化物・塩基性酸化物・両性酸化物(違い・見分け方・一覧・反応など)
❷ 水酸化物
- 水酸化物イオンOHーを含む化合物を水酸化物という。
- 例としては,NaOHやCa(OH)2などが挙げられる。
❸ オキソ酸
- 酸素O原子を含む酸をオキソ酸という。
- 例としては,H2SO4・HNO3・H2CO3などが挙げられる。
❹ 塩
- 酸由来の陰イオンと塩基由来の陽イオンからなる化合物を塩という。
- 塩には酸性塩・塩基性塩・正塩の3種類があり,例としてはNaHCO3,CuCl(OH),NaClなどがあげられる。
無機物まとめ
この『無機物(分類・有機物との違いなど)』のページで解説した内容をまとめる。

演習問題
化学のグルメでは、高校化学・化学基礎の一問一答問題を公開しています。問題一覧は【スマホで出来る】一問一答(高校化学・化学基礎)でご覧下さい。
問1
有機物とは【1】原子を含む化合物の総称である。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】炭素C
有機物(有機化合物)は炭素C原子を含む化合物の総称である。
問2
無機物のうち,1種類の元素からなる物質を【1】という。
解答/解説:タップで表示
問3
無機物のうち,2種類以上の元素からなる物質を【1】という。
解答/解説:タップで表示
問4
酸化された化合物を【1】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】酸化物
酸化された化合物を酸化物という。
酸化物には酸性酸化物・塩基性酸化物・両性酸化物があり,例としてはCO2・CaO・Al2O3などがあげられる。
問5
水酸化物イオンOHーを含む化合物を【1】という。
解答/解説:タップで表示
問6
酸素O原子を含む酸を【1】という。
解答/解説:タップで表示
問7
酸由来の陰イオンと塩基由来の陽イオンからなる化合物を【1】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】塩
酸由来の陰イオンと塩基由来の陽イオンからなる化合物を塩という。
塩には酸性塩・塩基性塩・正塩の3種類があり,例としてはNaHCO3,CuCl(OH),NaClなどがあげられる。