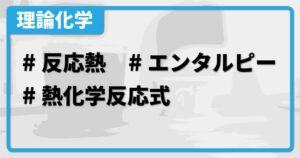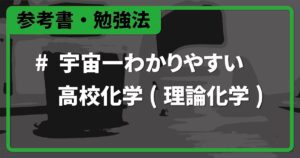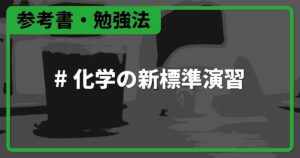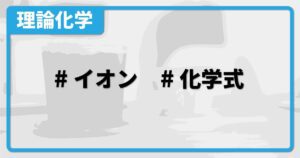MENU
酸性塩・塩基性塩・正塩(違い・見分け方・一覧など)
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『酸性塩・塩基性塩・正塩(違い・見分け方・一覧など)』について解説しています。
塩の分類
- 中和の結果生成する”塩”には酸性塩・塩基性塩・正塩の3種類存在する。
| 酸性塩 | 酸由来のH+が残っている塩 |
| 塩基性塩 | 塩基由来のOHーが残っている塩 |
| 正塩 | H+もOHーも残っていない塩 |
- 酸由来のH+が残っている塩を酸性塩という。具体例としては、NaHCO3(NaとCの間のH)・NaHSO4(NaとSの間のH)などが挙げられる。
- 塩基由来のOHーが残っている塩を塩基性塩という。具体例としては、CuCl(OH)・MgCl(OH)などが挙げられる。
- 余分なH+やOHーが残っていない塩を正塩という。具体例としては、NaCl・CaCl2・CH3COONaなどが挙げられる。
塩の分類と液性
- 塩の種類と、その塩を水に溶かしたときの“液性(酸性or塩基性or中性)”は必ずしも一致するわけではない。
- このあたりについては次のページを参照のこと。
中和まとめ
この『酸性塩・塩基性塩・正塩(違い・見分け方・一覧など)』のページで解説した内容をまとめる。
- 酸由来のH+が残っている塩を酸性塩という。
- 塩基由来のOHーが残っている塩を塩基性塩という。
- 余分なH+やOHーが残っていない塩を正塩という。
演習問題
化学のグルメでは、高校化学・化学基礎の一問一答問題を公開しています。問題一覧は【スマホで出来る】一問一答(高校化学・化学基礎)でご覧下さい。
問1
酸由来のH+が残っている塩を【1】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】酸性塩
酸由来のH+が残っている塩を酸性塩という。
具体例としては、NaHCO3(NaとCの間のH)・NaHSO4(NaとSの間のH)などが挙げられる。
問2
塩基由来のOHーが残っている塩を【1】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】塩基性塩
塩基由来のOHーが残っている塩を塩基性塩という。
具体例としては、CuCl(OH)・MgCl(OH)などが挙げられる。
問3
余分なH+やOHーが残っていない塩を【1】という。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】正塩
余分なH+やOHーが残っていない塩を正塩という。
具体例としては、NaCl・CaCl2・CH3COONaなどが挙げられる。
問4
NaHCO3は【1(酸性 or 塩基性 or 正)】塩である。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】酸性
NaHCO3は酸性塩である。
問5
CuCl(OH)は【1(酸性 or 塩基性 or 正)】塩である。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】塩基性
CuCl(OH)は塩基性塩である。
問6
CaCl2は【1(酸性 or 塩基性 or 正)】塩である。
解答/解説:タップで表示
解答:【1】正
CaCl2は正塩である。