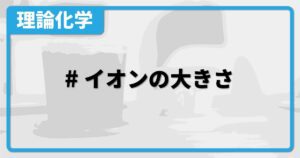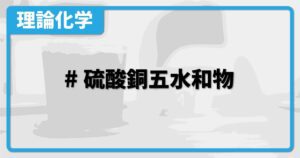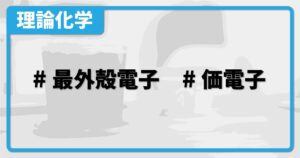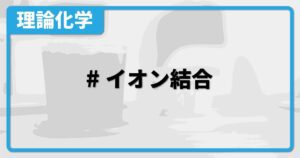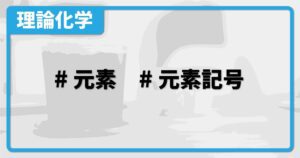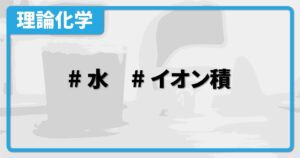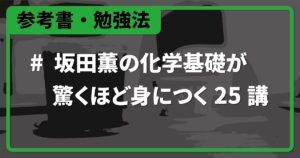MENU
元素と単体の違い(具体例・見分け方・例題・問題など)
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『元素と単体の違い(具体例・見分け方・例題・問題など)』について解説しています。
単体とは
- 純物質のうち、1種類の元素からなる物質を単体という。単体の具体例としては、O2、H2、N2、Feなどが挙げられる。
ちなみに、純物質のうち、2種類以上の元素からなる物質を化合物といいます。化合物の具体例としては、H2O、NH3、NaClなどが挙げられます。
元素とは
- 物質をつくる基本的な成分を元素という。
- 具体例としては、H(水素)やC(炭素)、O(酸素)などが挙げられる。元素記号そのままであることに注目しよう。
イメージとしては次のとおりである。
- 単体の「H2(水素)」という物質の構成成分である「H(水素)」
- 単体の「O2(酸素)」という物質の構成成分である「O(酸素)」
- 単体の「C(黒鉛やダイヤモンド)」という物質の構成成分である「C(炭素)」
単体と元素の違い・見分け方
| 元素 | 触れることができない |
| 単体 | 触れることができる |
- 元素は物質の構成成分、単体は1種類の元素からなる物質を指す。
- したがって、単体は実在する物質そのものなので触れることができ、元素はあくまで構成成分なので直接触れることができない。
- 「元素か単体か」を問われたときは「実際に触れることができるのか」を基準に考えよう。
問題
太字部分が「元素」か「単体」かを見分けよ。
地殻中には酸素が多く含まれている。
- この文中で実際に触れることができるのは地殻である。
- 酸素は地殻の構成成分で触れることはできないので元素である。
演習問題
問1
太字部分が「元素」か「単体」かを見分けよ。
その患者は酸素吸入を受けながら搬送された。
解答/解説:タップで表示
解答:単体
ここでは実際に存在する気体の酸素O2を吸入している。
触れることができるので空気中の酸素と同じであり、したがって単体である。
問2
太字部分が「元素」か「単体」かを見分けよ。
アンモニアは、窒素と水素から合成されている。
解答/解説:タップで表示
解答:単体
アンモニアは次の反応式のように気体の水素H2と気体のN2から合成される。
\[ \mathrm{3H_{2} + N_{2} → 2NH_{3}} \]
気体の水素は触れることができるので、単体である。
問3
太字部分が「元素」か「単体」かを見分けよ。
カルシウムは骨や歯に多く含まれている。
解答/解説:タップで表示
解答:元素
カルシウムは、骨や歯にリン酸カルシウムCa3(PO4)2として含まれている。
カルシウム自体は、リン酸カルシウムの構成成分の1つであり、直接触れることができない。
したがって、単体ではなく元素である。