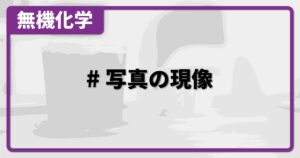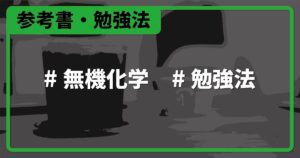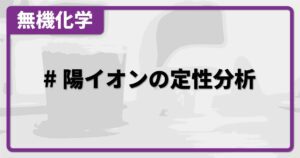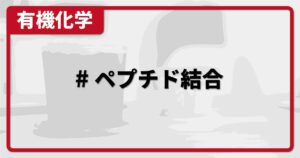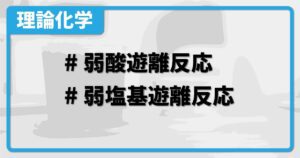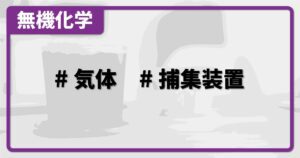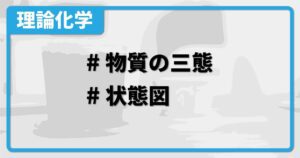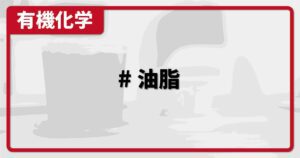MENU
ハーバー法(ハーバー・ボッシュ法)の原理・反応式・高温高圧下の理由など
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『ハーバー法(ハーバー・ボッシュ法)の原理・反応式・高温高圧下の理由など』について解説しています。
ハーバー法(ハーバー・ボッシュ法)
- 窒素N2は非常に安定しており、ほとんど化合物を作らないことで有名である。
- 窒素元素は肥料の三要素の1つであり、固定化して植物に与える必要があったため、研究者は苦難していた。そんな中、20世紀の初め頃、ドイツのフリッツ・ハーバーとカール・ボッシュによってアンモニアNH3の製法であるハーバー法(ハーバー・ボッシュ法)が開発された。
- この方法では、四酸化三鉄Fe3O4を触媒に用い、高温高圧下で次の反応を進める。
\[ \mathrm{N_{2}+3H_{2} \overset{触媒(Fe_{3}O_{4})}{→} 2NH_{3}} \]
ハーバー・ボッシュ法を高圧下で行う理由
- ハーバー・ボッシュ法を高圧下で行うのは、平衡時のアンモニアNH3の吸収率を上げるためである。
- 先述のように、ハーバー・ボッシュ法の反応式は次の通りである。
\[ \mathrm{N_{2}+3H_{2} \overset{触媒(Fe_{3}O_{4})}{→} 2NH_{3}} \]
- この反応は可逆的反応であり、一定の条件下で平衡状態に達する。
- 式の左右の気体分子数を比較すると、左>右である。したがって、ルシャトリエの原理より、高圧下では気体分子数が減少する方向、つまり右方向に反応が進む。
- その結果、NH3を効率よく回収できる。
参考:可逆反応と不可逆反応
ハーバー・ボッシュ法を高温下で行う理由
- ハーバー・ボッシュ法を行う際の温度は、2つの観点から考える必要がある。
反応速度
- 一般に、温度を上げると反応速度が大きくなる(参考:反応速度が変化する要因)。
- その結果、平衡状態に達するのがはやくなり、効率よくアンモニアNH3を回収できる。
ルシャトリエの原理
- 一方、この反応は発熱反応である。
\[ \mathrm{N_{2}+3H_{2} \overset{触媒(Fe_{3}O_{4})}{→} 2NH_{3}\color{#dc143c}{ +92kJ }} \]
- したがって、温度を下げると、ルシャトリエの原理により発熱方向に反応が進むため、効率よくNH3を回収できる。
結論
- 2つの観点を総合的に考え、ハーバー・ボッシュ法は、中程度の温度(約500℃)で行う。
- また、反応速度を大きくするため、触媒としてFe3O4を用いる。