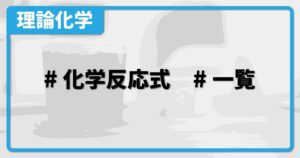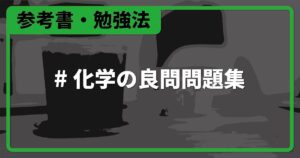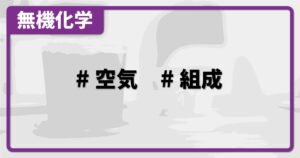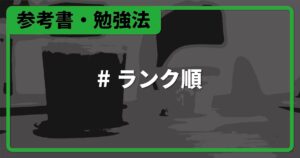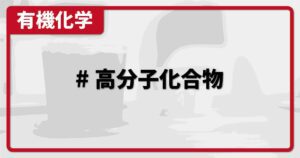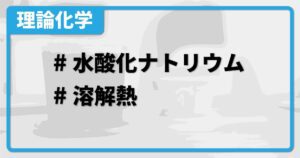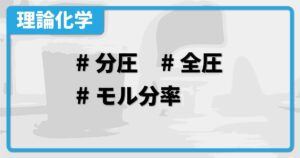MENU
接触法(濃硫酸の工業的製法・仕組み・反応式・触媒など)
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『接触法(濃硫酸の工業的製法・仕組み・反応式・触媒など)』について解説しています。
接触法の仕組み
- 濃硫酸の工業的製法を接触法という。
- 接触法の仕組みは次の通りである。
- まずは、硫黄Sを燃焼させることで二酸化硫黄SO2を得る。
\[ \mathrm{S + O_{2} → SO_{2} }\]
黄銅鉱(二硫化鉄)FeS2の燃焼
一昔前は、硫黄の燃焼ではなく、黄銅鉱(二硫化鉄)FeS2の燃焼により二酸化硫黄SO2を得ていた。
\[ \mathrm{4FeS_{2} + 11O_{2} → 2Fe_{2}O_{3} + 8SO_{2} }\]
次に、STEP1で得たSO2を空気中のO2によって酸化させることで三酸化硫黄SO3を得る。
\[ \mathrm{2SO_{2}+O_{2} \overset{酸化バナジウム(Ⅴ)V_{2}O_{5}}{\rightleftarrows}2SO_{3}} \]
SO3の生成効率を上げる方法
この段階において三酸化硫黄SO3の生成効率を高めるには、低温・高圧にする。
\[ \mathrm{2SO_{2}+O_{2} \overset{低温・高圧}{\color{ #ff0000 }{→}}2SO_{3}} \]
低温にすると、ルシャトリエの原理により温度を上げる方向に反応が進む。この反応は発熱反応なので、右(SO3が生成する方向)に反応が進む。
画像
高圧にすると、ルシャトリエの原理により圧力を下げる方向(気体分子数が少なくなる方向)に反応が進む。この反応における気体分子数を比較すると、左は3、右は2なので、右に反応が進む。
最後に、STEP2で得たSO3を濃硫酸に溶かして発煙硫酸とし、そこに希硫酸を加えることで濃硫酸を得る。(発煙硫酸中のSO3と希硫酸中のH2Oが反応する)
\[ \mathrm{SO_{3} + H_{2}O → H_{2}SO_{4}} \]
発煙硫酸とは
発煙硫酸とは、濃硫酸H2SO4に大量の三酸化硫黄SO3を吸収させたものである。
発煙硫酸は、SO3の蒸気を発している。
SO3を水に吸収させると、溶解熱により水が一気に沸騰する。このとき発生する水蒸気にSO3が溶け、硫酸の霧ができる。しかし、硫酸分子は水分子と比較して極めて大きいため、この霧は水中で拡散しにくい(溶けにくい)。
したがって、発熱を抑えるため、濃硫酸中の水にゆっくりとSO3を吸収させて発煙硫酸をつくり、これを希硫酸で薄めることで目的の濃度の濃硫酸をつくる。
画像
接触法まとめ
この『接触法(濃硫酸の工業的製法・仕組み・反応式・触媒など)』のページで解説した内容をまとめる。
- 濃硫酸の工業的製法を接触法という。
- 接触法の仕組みは次の通りである。
❶ 硫黄Sを燃焼させることで二酸化硫黄SO2を得る。
❷ STEP1で得たSO2を空気中のO2によって酸化させることで三酸化硫黄SO3を得る。
❸ STEP2で得たSO3を濃硫酸に溶かして発煙硫酸とし、そこに希硫酸を加えることで濃硫酸を得る。