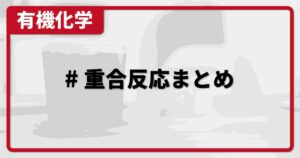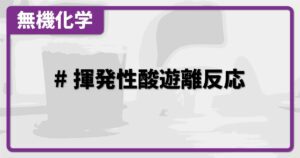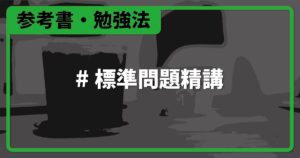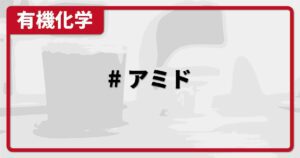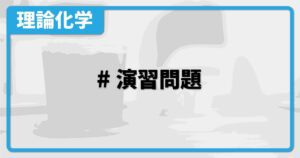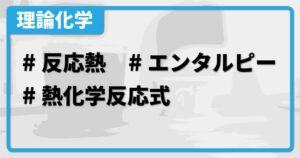MENU
突沸(原理・防ぐ方法・沸騰石など)
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『突沸(原理・防ぐ方法・沸騰石など)』について解説しています。
突沸が起こる理由
- 蒸発と沸騰(違い・蒸気圧との関係など)にあるように、沸騰は溶媒内部の「気泡」が原因となって起こる。この気泡は容器の壁面(無数の凹凸がある)に付着している場合が多い。
- 一度煮沸の処理をして溶存気体を取り除いた液体を異物の付着がなく、また凹凸の少ない容器を用いて加熱した場合、沸点に達してもなかなか沸騰しないことがある。これを過熱という。
- 過熱状態が続き、ある限度を超えると、突然大きな気泡を生じ激しい沸騰が起こることがある。これを突沸という。
- 突沸がおこると高温の液体が周囲に飛び散るので非常に危険である。
- 突沸を防ぐためのツールとして沸騰石とよばれる“石”がある。
沸騰石とは
- 多孔質の素焼きの小片を沸騰石という。
- これを液体に入れて加熱すると少しずつ(沸騰の元になる)空気の小泡を放出するので、継続して沸騰を起こすことができ突沸を防ぐ効果がある。
沸騰石は乾燥して用いる
- 沸騰石が空気の小泡を放出するのは、沸騰石がもつ小さな無数の穴に空気を溜め込んでいるからである。
- したがって、沸騰石は濡れている状態だと(穴に空気の代わりに水が入っているため)使い物にならない。使用の際は「よく乾燥しているか」を確認する必要がある。