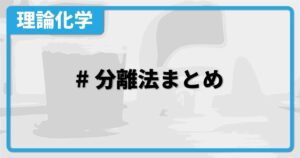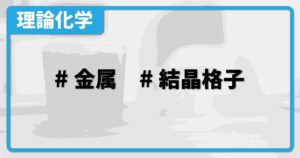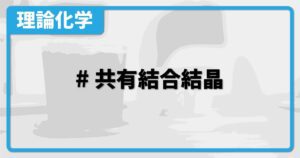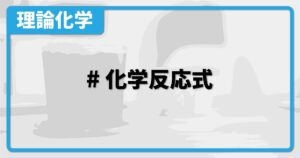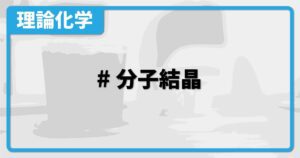MENU
【塩の加水分解】塩の液性が酸性・塩基性になる理由
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『塩の液性(見分け方・演習問題など)』について解説しています。
塩の加水分解とは
- 強酸と弱塩基からできた塩を水に溶かした場合、その水溶液の液性は酸性に、弱酸と強塩基からできた塩を水に溶かした場合、水溶液の液性は塩基性になる。
- 参考:塩の液性(見分け方・演習問題など)
- これは「塩の加水分解(水H2Oとの反応)」が原因である。
- ここでは、強酸と弱塩基からできた塩として塩化アンモニウムNH4Cl、弱酸と強塩基からできた塩として酢酸ナトリウムCH3COONaを使って解説する。
塩化アンモニウムNH4Clの加水分解
- NH4Clの加水分解は次の反応式で表すことができる。
\[ \mathrm{NH_{4}Cl + H_{2}O ⇄ NH_{3}+ H_{2}O + HCl} \]
- NH4Cl(塩)とHCl(強酸)は電離度が大きいため完全に電離するが、H2OとNH3(弱塩基)は電離度が小さくほとんど電離しない。したがって、次のように考えることができる。
\[ \begin{align}&\mathrm{NH_{4}^{+} + \cancel{Cl^{-}} + H_{2}O ⇄ NH_{3} +} \underbrace{ \mathrm{H_{2}O + H^{+} }}
_{ \mathrm{H_{3}O^{+}} } + \cancel{\mathrm{Cl^{-}}} \\
&\mathrm{↔︎ NH_{4}^{+} + H_{2}O ⇄ NH_{3} +} \underbrace{ \mathrm{H_{3}O^{+}} }
_{ \text{ 酸性 } } \end{align}\]
- Clーは両辺に存在するので消すことができる。また、H2OとH+が組み合わさってできるH3O+は酸性を示すため、結果的に水溶液の液性は酸性となる。
酢酸ナトリウムCH3COONaの加水分解
- CH3COONaの加水分解は次の反応式で表すことができる。
\[ \mathrm{CH_{3}COONa + H_{2}O ⇄ CH_{3}COOH + NaOH } \]
- CH3COONa(塩)とNaOH(強塩基)は電離度が大きいため(ほぼ)完全に電離するが、H2OとCH3COOH(弱酸)は電離度が小さく(ほぼ)電離しない。したがって、次のように考えることができる。
\[ \begin{align}&\mathrm{CH_{3}COO^{-} + \cancel{Na^{+}} + H_{2}O ⇄ CH_{3}COOH + \cancel{Na^{+}} + OH^{-} \ } \\
&\mathrm{↔︎ CH_{3}COO^{-} + H_{2}O ⇄ CH_{3}COOH +} \underbrace{ \mathrm{OH^{-}} }
_{ \text{ 塩基性 } }\end{align}\]
- Na+は両辺に存在するので消すことができる。また、OH–が存在するため結果的に水溶液の液性は塩基性となる。