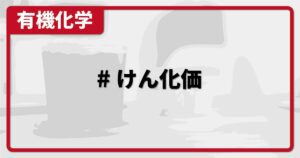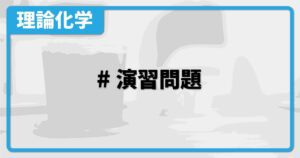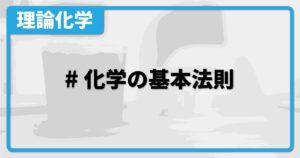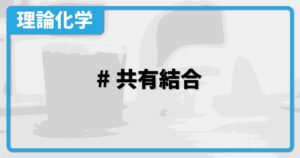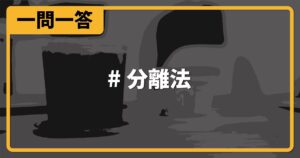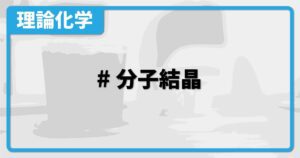MENU
気体反応の法則(例・発見者・演習問題など)
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『気体反応の法則(例・発見者・演習問題など)』について解説しています。
気体反応の法則
- 気体同士が反応したり、反応によって気体が生成するとき、それらの気体の体積間には簡単な整数比が成り立つ。この法則を気体反応の法則という。
- 例として、①水素と窒素によるアンモニアの生成反応、②一酸化炭素と酸素による二酸化炭素の生成反応、③水素と塩素による塩化水素の生成反応を見ていこう。
① 水素と窒素によるアンモニアの生成反応
- 水素H2と窒素N2を反応させるとアンモニアNH3が生成する。
\[ \mathrm{3H_{2}+N_{2}→2NH_{3}} \]
- このとき、H2、N2、NH3の3つの気体間には、次のようなmol比が成り立つ。
\[ \underbrace{ \mathrm{3H_{2}} }
_{ \text{ 3(mol) }}
+
\underbrace{ \mathrm{N_{2}} }
_{ \text{ 1(mol) }}
→
\underbrace{ \mathrm{2NH_{3} }}
_{ \text{ 2(mol) }} \]
※化学反応式(係数・作り方・書き方・計算問題の解き方など)にあるように、mol比は化学反応式の係数比と一緒になる。
- ここで、標準状態における気体1molあたりの体積が22.4(L/mol)であることを考えると、各気体の体積(L)が簡単な整数比になっているのがわかる(3:1:2)。
\[ \underbrace{ \mathrm{3H_{2}} }
_{ \text{ 3(mol)×22.4(L/mol)=67.2(L) }}
+
\underbrace{ \mathrm{N_{2}} }
_{ \text{ 1(mol)×22.4(L/mol)=22.4(L) }}
→
\underbrace{ \mathrm{2NH_{3}} }
_{ \text{ 2(mol)×22.4(L/mol)=44.8(L) }} \]
参考:アボガドロの法則(定義・発見者・mol計算、気体計算との関係)
② 一酸化炭素と酸素による二酸化炭素の生成反応
- 一酸化炭素COと酸素O2が反応すると二酸化炭素CO2が生成する。
\[ \mathrm{2CO+O_{2}→2CO_{2}} \]
- このとき、CO、O2、CO2の3つの気体の間には次のようなmol比が成り立つ。
\[ \underbrace{ \mathrm{2CO} }
_{ \text{ 2(mol) }}
+
\underbrace{ \mathrm{O_{2}} }
_{ \text{ 1(mol) }}
→
\underbrace{ \mathrm{2CO_{2}} }
_{ \text{ 2(mol) }} \]
- 先ほどと同じように、標準状態では気体1molあたりの体積が22.4(L/mol)であることを考慮すると、次のようになる。
\[ \underbrace{ \mathrm{2CO} }
_{ \text{ 2(mol)×22.4(L/mol)=44.8(L) }}
+
\underbrace{ \mathrm{O_{2}} }
_{ \text{ 1(mol)×22.4(L/mol)=22.4(L) }}
→
\underbrace{ \mathrm{2CO_{2}} }
_{ \text{ 2(mol)×22.4(L/mol)=44.8(L) }} \]
- 各気体の体積(L)が簡単な整数比(2:1:2)になっていることが理解できる。
③水素と塩素による塩化水素の生成反応
- 水素H2と塩素Cl2を反応させると塩化水素HClが生成する。
\[ \mathrm{H_{2}+Cl_{2}→2HCl} \]
- このとき、H2、Cl2、HClの3つの気体の間には次のようなmol比が成り立つ。
\[ \underbrace{ \mathrm{H_{2}} }
_{ \text{ 1(mol) }}
+
\underbrace{ \mathrm{Cl_{2}} }
_{ \text{ 1(mol) }}
→
\underbrace{ \mathrm{2HCl} }
_{ \text{ 2(mol) }} \]
- 標準状態では気体1molあたりの体積が22.4(L/mol)であることを考慮すると、次のようになる。
\[ \underbrace{ \mathrm{H_{2}} }
_{ \text{ 1(mol)×22.4(L/mol)=22.4(L) }}
+
\underbrace{ \mathrm{Cl_{2}} }
_{ \text{ 1(mol)×22.4(L/mol)=22.4(L) }}
→
\underbrace{ \mathrm{2HCl} }
_{ \text{ 2(mol)×22.4(L/mol)=44.8(L) }} \]
- 各気体の体積(L)が簡単な整数比(1:1:2)になっていることが理解できる。
気体反応の法則の発見者・発見年
- 気体反応の法則の発見者はゲーリュサック、発見した年は1808年である。
演習問題
化学のグルメでは、高校化学・化学基礎の一問一答問題を公開しています。問題一覧は【スマホで出来る】一問一答(高校化学・化学基礎)でご覧下さい。
気体反応の法則について、簡単に説明せよ。
解答/解説:タップで表示
解答:下記参照
気体同士が反応したり、反応によって気体が生成するとき、それらの気体の体積間には簡単な整数比が成り立つ。この法則を気体反応の法則という。
気体反応の法則の発見者、発見した年を述べよ。
解答/解説:タップで表示
解答:ゲーリュサック/1808年
気体反応の法則の発見者はゲーリュサック、発見した年は1808年である。