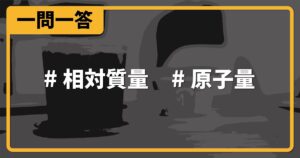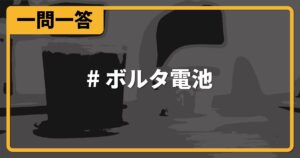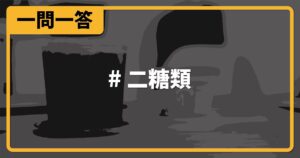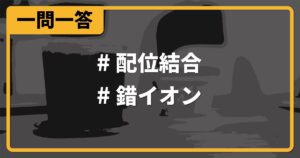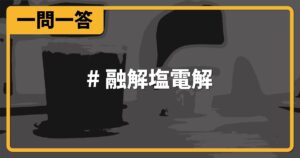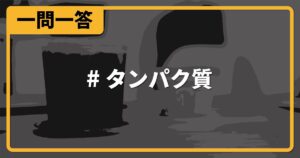MENU
イオン結合【高校化学・化学基礎一問一答】
問1
陽イオンであるナトリウムイオンNa+と陰イオンである塩化物イオンClーは【1】力によって結合する。
解答/解説:タップで表示
問2
クーロン力による陽イオンと陰イオンの結合を【1】という。
解答/解説:タップで表示
問3
イオン結合は陽性の強い【1(金属 or 非金属)】元素と陰性の強い【2(金属 or 非金属)】元素の結合である。
解答/解説:タップで表示
問4
イオン結合でできた結晶を【1】という。
解答/解説:タップで表示
問5
イオン結晶は陽イオンと陰イオンの数の比を表す【1】で表される。
解答/解説:タップで表示
問6
次のイオン結晶の組成式を書け。
塩化ナトリウム:【1】
塩化カルシウム:【2】
解答/解説:タップで表示
問7
イオン結晶は融点が【1(高 or 低)】く、【2(硬 or 柔らか)】いが、強く叩くと簡単に割れてしまう。
解答/解説:タップで表示
問8
イオン結晶は、結晶の状態では基本的に電気を通さず、【1】すると電気を通すようになる。
解答/解説:タップで表示
問9
イオン結晶が水に溶けて各イオンに分かれる現象を【1】といい、このような物質を【2】という。
解答/解説:タップで表示
問10
イオン結晶は結晶全体として、電気的に【1】性である。