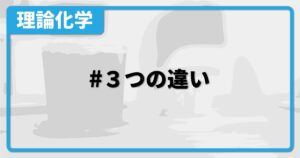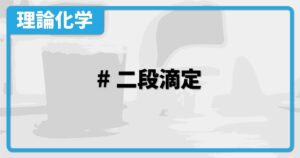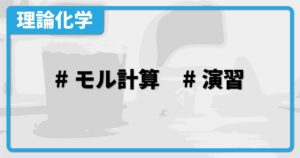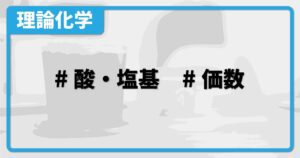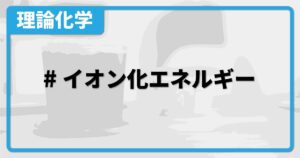MENU
倍数比例の法則(例・発見者・問題の解き方など)
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『倍数比例の法則(発見者・例・グラフ・硫酸銅の問題の解き方など)』について解説しています。
倍数比例の法則とは
- A、Bの2元素から成る化合物が2種類以上あるとき、一定量のAと化合しているBの質量はこれらの化合物の間で簡単な整数比が成り立つ。これを倍数比例の法則という。
- 例として、単体の銅を燃焼させたときにできる酸化銅(Ⅰ)と酸化銅(Ⅱ)を使って説明する。
| 酸素 | 銅 | |
|---|---|---|
| 酸化銅(Ⅰ) | 16g | 128g |
| 酸化銅(Ⅱ) | 16g | 64g |
- 一定量(16g)の酸素と化合している銅の質量は「2:1(128:64)」という簡単な整数比になっている。
- O、Cuの2元素からなる化合物が2種類あり、一定量のOと化合しているCuの質量はこれらの化合物の間で簡単な整数比になっており、倍数比例の法則が成り立っているといえる。
倍数比例の法則の発見者・発見年
- 倍数比例の法則の発見者はドルトンであり、発見した年は1803年である。
演習問題
化学のグルメでは、高校化学・化学基礎の一問一答問題を公開しています。問題一覧は【スマホで出来る】一問一答(高校化学・化学基礎)でご覧下さい。
問1
倍数比例の法則について、簡単に説明せよ。
解答/解説:タップで表示
解答:下記参照
A、Bの2元素から成る化合物が2種類以上あるとき、一定量のAと化合しているBの質量はこれらの化合物の間で簡単な整数比が成り立つ。これを倍数比例の法則という。
問2
倍数比例の法則の発見者、発見した年を述べよ。
解答/解説:タップで表示
解答:ドルトン/1803年
倍数比例の法則の発見者はドルトンであり、発見した年は1803年である。